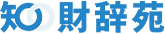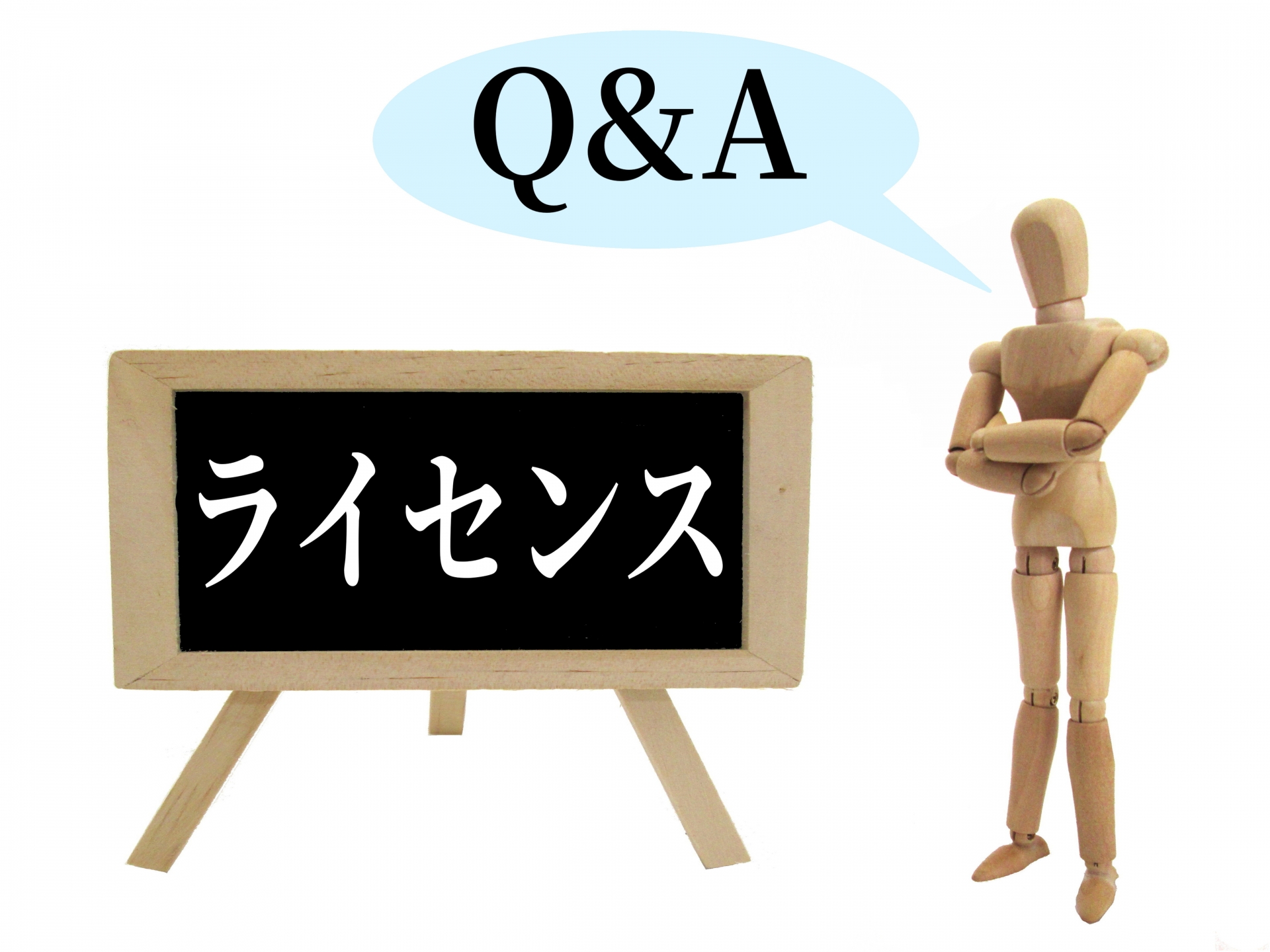「特許を取得して、ライセンス料を取得したい!」、「他社の特許技術の使用許諾が欲しい!」と考える方も多いのではないでしょうか?
今回は、今まで書いてきたライセンス関連の記事をまとめました。
特許権を活かしたビジネスモデルとして挙げられる第三者への許諾。
第三者への許諾に対してロイヤリティを得ることで収益となりますが、ロイヤリティはいくらに設定すれば良いのでしょうか?
フランチャイズ契約には必ずといってもいいほど「ロイヤリティ」という用語が登場します。
フランチャイズ事業は自社の商標やノウハウといった知的財産の使用を他者に許諾することで成立するビジネであり、ライセンスを活かしたビジネスモデルだといえるでしょう。
ここで、ロイヤリティと同じように使われる用語として「ライセンスフィー」というものがあります。
知的財産の分野におけるロイヤリティとライセンスフィーにはどのような違いがあるのでしょうか?
特許ライセンスの交渉は知財担当者の悩みどころであり、また手腕を見せる場ともなるでしょう。
自社の活路を開く場面で決断を迫られることも多い特許ライセンスですが、交渉においてはどのような気構えで向かうべきなのでしょうか?
今回は、特許を持っているライセンサーの立場で、他社にライセンスをする場合のライセンス交渉のコツを紹介します。
ライセンス契約は、ライセンサーにのみ有利でライセンシーにとって著しく不利な条件を付されることも珍しくありません。
ライセンス契約を締結する際に自社が著しく不利な状況に陥らないための契約書の読み取り方についてライセンシー側の視点から紹介します。
ある知的財産権について、権利者から実施の許諾を受ける契約をライセンス契約といいます。
ところが、ライセンス契約を締結して、許諾を受けたライセンシーが、実際に製品を製造する段階になってある問題が生じることがあります。
自社・自身が自ら特許を実施して利益を得るには、設備や人員への投資が必要となります。
それと比べると、ライセンス契約は他者の実施によって利益を得ることが可能となるため、発明の収益化の手段としてはハードルが低いというイメージがあるでしょう。
これから特許権を活かしてライセンス契約をビジネスにしようと検討している企業法人の担当者は、どのような点に注意しておくべきでしょうか?
ライセンス契約は、第三者に実施を許諾するだけで利益を得るイメージになりがちですが、思わぬ損害を被ることもあります。
ライセンス契約で損をしないためのポイントをまとめました。
特許といえば、ある一つの発明について世間に公開することを条件に、一定の期間に限って実施を独占する権利を有することを意味します。
しかし、新技術が導入されることが多いパソコンや携帯電話・スマートフォンなどの電子機器のように、数多くの部品によって1つの機器が構成されている製品では、1つの機器の中に数百個以上の特許が盛り込まれていることが多々あります。
9.商標のライセンス契約、契約書に絶対に記載するべき事項とは
商標のライセンス契約は、商標がビジネスに直結して使用されることが多いという特性を持っておりトラブルに発展することも少なくありません。
商標ライセンスにおけるトラブルを回避するために有効なライセンス契約書作成上の必須記載事項について紹介します。
フランチャイズ契約とライセンス契約は対価を支払って他者のブランド力を使用するという点で共通していますが、経営の自由度や本部からのサポートに差があります。
両者の違いを解説しましょう。
11.意匠のライセンス契約 契約書に絶対に記載するべき事項とは
意匠のライセンス契約は意匠権を活用したビジネスの幅を広げる一つの手法です。
知財のライセンス契約はトラブルに発展することが多いので、契約書に必須の記載事項をチェックしておきましょう。
爆発的に普及しているスマートフォンやタブレットなどは、1機の端末に数多くの海外特許が埋め込まれています。
製品の製造・販売のグローバル化が目立つ昨今では、海外企業とのライセンス契約を締結する場面も増えてきたため、企業の大小を問わず海外企業とのライセンス契約についての知識を固めておくべきでしょう。
ここでは海外企業とのライセンス契約をおこなう際の留意点について紹介します。
近年、地方から発信される『ご当地キャラ』や『ゆるキャラ』などが浸透し、オリジナルキャラクターを権利化する意識が向上しています。
一方で、どんな場合でもオリジナルキャラクターを権利化すれば収益が得られるという誤解も生じているため、キャラクターを取り巻く知的財産保護のかんがえかたについては、改めて理解を深めておく必要があるでしょう。
ここでは、アニメキャラクターなどをはじめとした「キャラクター使用におけるライセンス契約の留意点」について、使用許諾を受ける側、使用を許諾する側の両面からみていきましょう。
13億人もの人口を抱える中国の市場が日本企業において重要な位置付けであることは、すでに既知の事実でしょう。
技術力が高い日本企業にとって、強力な生産力と広い市場を持つ中国企業と連携する機会は増えています。
その中で、中国企業との技術ライセンス契約の締結を検討場面もまた多いことでしょう。
ただし、中国企業との技術ライセンス契約を締結する際には、国内または中国以外の諸外国の企業と技術ライセンス契約を締結する場合とは別に、特段の注意点が存在します。
ここでは、中国企業と技術ライセンス契約をおこなう際の注意点を紹介します。
特許・商標・意匠などの知的財産権の実施を他者に許諾する契約がライセンス契約です。
ライセンス契約を結ぶ際に交わす契約書には、必ず「保証事項」の記載があります。
ライセンス契約書における保証事項とはどのような意味があり、どんな効力があるのでしょうか?
ライセンス契約によって実施を許諾する側、許諾を受ける側、両面からみた保証事項の意義を解説します。
特許権には「産業上の利用可能性」という要件があります。
産業の発展が期待できる発明こそ特許権が与えられるということです。
特許権は一定期間の発明の独占を約束しますが、その先には広く発明を利用して産業の発展に寄与することが期待されているわけです。
つまり、特許権によって独占が認められてはいますが、発明は広く利用されるべきだという背景がベースにあるわけです。
そこで登場するのがライセンス契約です。
近年、業務提携を活用した相乗効果の獲得や競争力の強化を目指すケースが増えています。
そして、業務提携の一形態を担う材料となるのが、知的財産権の実施許諾である「ライセンス契約」です。
ここでは、ライセンス契約を活用した業務提携について、その流れと方法をみていきましょう。
ライセンス契約の対象といえば登録済みの特許のみというイメージがあるかも知れませんが、特許出願中の状態でもライセンス契約は可能です。
特許出願中のライセンス契約について解説しましょう。