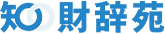目次
特許・商標・意匠などの知的財産権の実施を他者に許諾する契約がライセンス契約です。
ライセンス契約を結ぶ際に交わす契約書には、必ず「保証事項」の記載があります。
ライセンス契約書における保証事項とはどのような意味があり、どんな効力があるのでしょうか?
ライセンス契約によって実施を許諾する側、許諾を受ける側、両面からみた保証事項の意義を解説します。
≪ライセンス契約書における保証事項とは?≫
ライセンス契約は、実施許諾を受ける側が相応の対価を支払うか、または双方が知的財産権の使用を許諾しあうことで成立するものです。
つまり、実施が許諾される知的財産権は対価を支払う、または許諾を受ける側が自身の知的財産権についても実施を許諾するだけの価値があるものでなければなりません。
そのため、実施を許諾する側であるライセンサーとしては、次の項目を保証することになります。
・対象となっている知的財産権が適法に成立している
・対象となっている知的財産権を真にライセンサーが有している
・対象となっている知的財産権は、第三者の知的財産権を侵害していない
これらの項目が保証されていないと、許諾を受ける側であるライセンシーにとっては大きな不利益が生じるおそれがあります。
たとえば、いまだ知的財産権が認めらていないのに特許権を有しているかのように装ってライセンス料を支払わされているとすれば、非常に詐欺的な要素が強くなってしまいます。
また、知的財産権の権利者ではない者がライセンサーであるかのように偽っていれば契約自体に効力がなくなります。
ライセンサー自身が権利者であると認識していても、権利者について紛争が起きているようなケースでは、紛争のてん末次第ではライセンス契約自体が無効になるおそれもあります。
もし対象となっている知的財産権が第三者の知的財産権を侵害していれば、相手方に訴訟を起こされて無効になるだけでなく、損害賠償責任を追及されてしまう事態も起こり得ます。
保証事項とは、これらのトラブルが起こることのない、安全なライセンス契約であることを担保するための項目として活躍してくれるのです。
≪ライセンシーからみる保証事項の意義≫
ライセンシー側からみた場合の保証事項は、対価を支払ってまで許諾を受けた知的財産権の価値を担保することに意義があります。
まずはライセンス契約書のドラフトを受領した段階で、保証事項についての記載があるかをチェックしておく必要があります。
もし保証事項の記載がなければ必ず追加を要求するべきでしょう。
保証事項の記載があったとしても気を抜いてはいけません。
一応は保証事項の記載があっても、著しくライセンシーにとって不利な免責が加えられているおそれがあります。
各事項は保証しながらも「損害賠償責任は負わない」などの全面的な免責が加えられていれば保証事項が存在する意味がなくなってしまいます。
そんな形ばかりの保証事項は、記載だけあっても無意味です。
ライセンシー側としては、保証事項が守られなかった場合の責任の所在まで視野に入れた厳しいチェックが必要だと心得ておきましょう。
≪ライセンサーからみる保証事項の意義≫
ライセンサーとしては、自社が売り込もうとしている知的財産の健全性を表すという意義があります。
さらに、これが守られない場合はどのような責任を取っていくのかの姿勢も示すことで、対価を支払うライセンシーに安心を与える重要なセールスポイントでもあります。
ただし、不測のトラブルについて全ての責任を負うことを約束してしまうのは得策ではありません。
たとえば、特許権であればどのような理論展開で第三者が侵害を訴えてくるかを完全に予測して排除することは困難であって、いかなるトラブルも絶対に発生しないことまでは約束できるものではないのです。
ライセンサーとしては「当社が知る限り」などのように限定的な範囲を設けたり、免責事項を加えたりして、トラブル発生時の責任をすべて無条件で請け負うような解釈にならないように注意すべきでしょう。
≪保障事項のリーガルチェックは特許事務所に相談する≫
ライセンス契約書における保証事項は、ライセンシーにとっては価値のある取引きの担保であり、ライセンサーにとっては自社の知的財産の健全性を示す重要なものです。
どちらの立場にたっても必須となる項目ですが、一読するだけでは真意を読み取れないことが多いのも事実でしょう。
保証事項によってどこまでの保証が約束されるのか、どこまでの責任を負うのかなどを正確に解釈するには、知的財産のプロである弁理士によるリーガルチェックが必須です。
ライセンサー・ライセンシーのどちらの立場であれ、ライセンス契約の締結を検討している場合は、ドラフト段階であっても特許事務所に相談し、アドバイスを受けるのが賢明でしょう。
あわせて読みたい