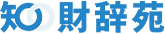目次
ライセンス契約の対象といえば登録済みの特許のみというイメージがあるかも知れませんが、特許出願中の状態でもライセンス契約は可能です。
特許出願中のライセンス契約について解説しましょう。
特許出願中でもライセンス契約は可能

特許庁での登録に至った特許権について、相応の対価を得る代わりに第三者に特許技術の実施を許諾するのが『ライセンス契約』です。
ライセンス契約においては、許諾する側(ライセンサー)のほうが許諾を受ける側(ライセンシー)よりも強い立場になることが多いので、ライセンシーの立場は法的に保護されているのです。
では、特許庁に出願はしているものの未だ登録に至っていない場合、つまり特許出願中の場合はどうなるのでしょうか?
結論をいえば、特許出願中の状態であっても第三者とライセンス契約を結ぶことは可能です。
特許権の存続期間は出願の日から20年間であり、出願から登録までの間は権利化が為されていない状態ではありますが、特許権者としてはこの期間も自らが発明を実施したりライセンス契約を結ぶなどして研究費用の回収や収益化につなげたいと考えるのも当然でしょう。
許諾を受けるライセンシーの立場としても、将来性のある特許であれば出願中であっても特許権者との良好な関係を構築したいと考えたり、流行の発明などであれば権利化を待っていてはビジネスチャンスを逃してしまうと考えた場合、たとえ特許出願中であってもライセンス契約を結んでおくことが得策となる場合があります。
特許出願中にライセンス契約を結ぶデメリット

特許出願中であってもライセンス契約を結ぶことは可能ですが、ライセンサー・ライセンシーの両者にとってのデメリットも存在します。
まずライセンサーにとっては、ライセンシーとの信用関係を維持するために契約上の注意点が発生します。
たとえばライセンス契約を交わした特許が特許庁から拒絶されてしまった場合、ライセンシーからライセンス料の返還を求められるおそれがあります。
この危険を回避するため、ライセンス契約書には支払い済のライセンス料を返還しない旨の不返還条項を盛り込んでおく必要があるでしょう。
特許出願中のライセンス契約で大きなデメリットを抱えるのはライセンシー側です。
ライセンシーの立場としての最大のデメリットは、まずライセンス料を支払ってまで実施の許諾を受けた発明が必ずしも権利化されるわけではないというリスクを抱えることです。
ライセンサーが不返還条項を提示しこれを了承していれば、支払い済のライセンス料の返還を求めることはできません。
すでに権利化された特許権であっても無効審判を受けるおそれがあることを考えれば同様のリスクを負いますが、いまだ権利化されていない特許はさらに不安定であり、あえてでもその不安定な特許に対して対価を支払うという大きなリスクを背負うことを理解しておく必要があるでしょう。
また、特許庁の審査によって請求範囲が狭まり、ライセンス契約をおこなった発明が特許権の範囲外になってしまうこともあります。
請求範囲が狭まったために許諾した発明が範囲外になってしまった場合は、ライセンシーに通知する旨の規定を盛り込んでおかないと、通知されないまま放置されて他者による実施を許してしまうおそれがあります。
さらに、特許権者が特許庁からの拒絶を受けても反論の余地があるのに諦めてしまったり、単なる懈怠によって審査請求をおこなわないなどの事態を防止するために、ライセンシーの同意なしでライセンサーが取下げなどをおこなわないよう手続きを遂行する義務を負わせることをライセンス契約書に明記しておくべきです。
特許出願中のライセンス契約でライセンシーを保護する仮通常実施権
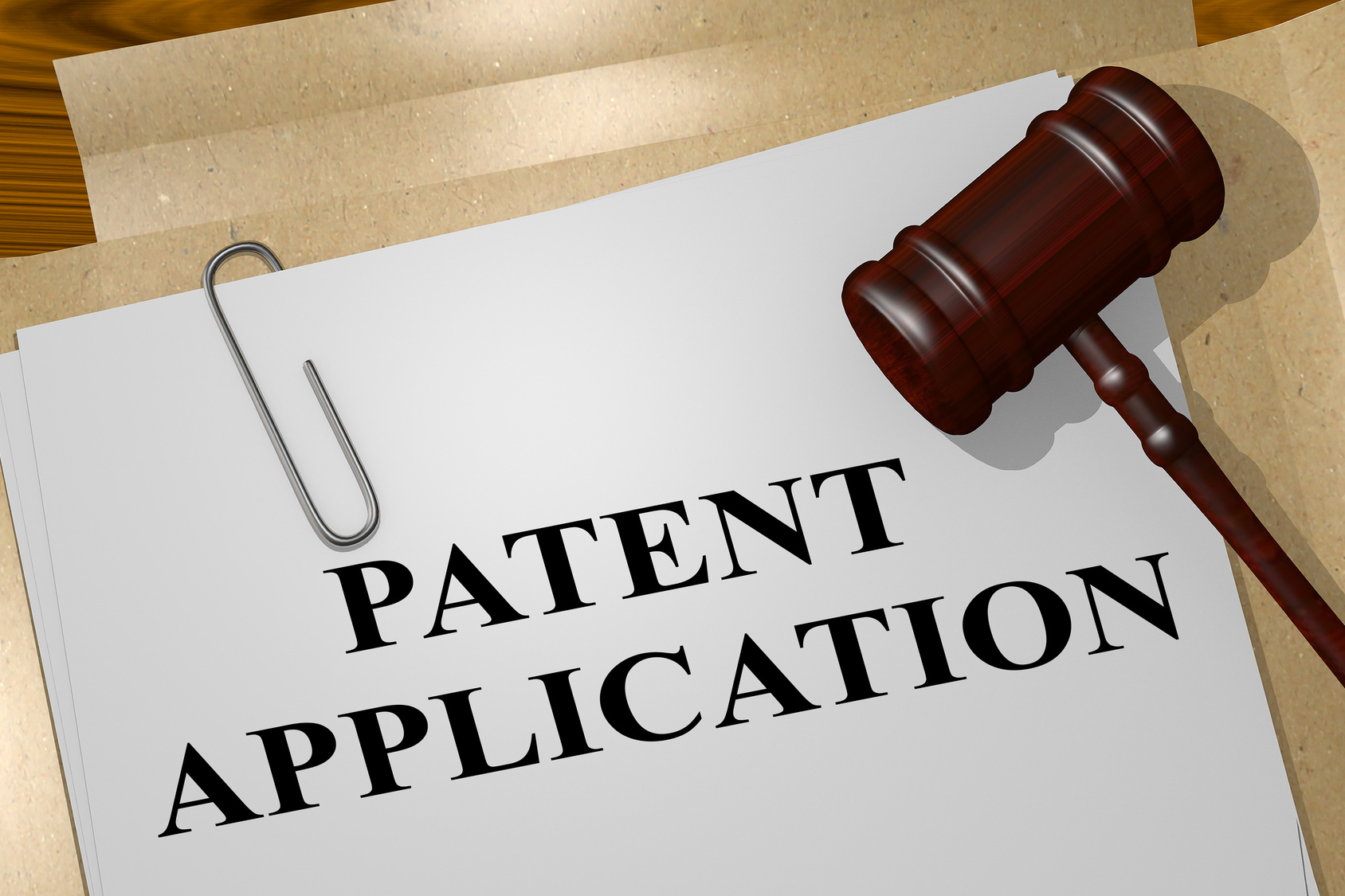
冒頭でも触れたとおり、通常実施権の設定をおこなえば、特許権者が他者に特許権を譲渡した場合でも、通常実施権者の立場は保護されて実施の許諾は継続されます。
ただし、これは権利化が実現してからの手続きであり、以前は特許出願中のライセンス契約についてライセンシーの立場は保護されていませんでした。
そのため2009年4月に『仮通常実施権』が認められることになりました。
仮通常実施権は、出願人が第三者に特許を受ける権利を譲渡した場合などでも、ライセンシーは実施の許諾が保護されるという制度です。
ここで、仮通常実施権を設定しておけば、特許が権利化された場合には通常実施権として扱われることになります。
仮通常実施権の存在は、ライセンシーにとっては安心感を、ライセンサーとしてはライセンシーの不安要素を排除する材料として非常に有効でしょう。
あわせて読みたい