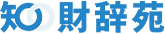目次
特許庁に特許出願をおこなうと、1年6か月後には出願内容が公開されます。
出願当時は権利化によって発明を保護しようと考えていても、1年以上もの時間が経過していれば事情が変わることもあるでしょう。
たとえば、特許出願はしたものの、特許化するよりも企業秘密のノウハウとして保護したほうが経営戦略上は得策であると判断することも珍しくはありません。
この場合、出願中の特許の手続きが進行するのを取りやめてもらうことになります。
ここで有効となるのが出願の「取り下げ」または「放棄」です。
特許出願の取り下げ・放棄の方法について解説しましょう。
≪特許出願の取り下げとは?≫
特許出願は、出願人の自由な意思によって取り下げが可能です。
特許権は出願人の財産とみなされるものであり、財産の処分は所有者の自由意志によっておこなわれるため、出願の取り下げも財産であればまた自由な処分であるという考え方に基づいています。
取り下げにはさまざまな事情が考えられます。
たとえば、冒頭で例に挙げたようにノウハウとして保護すると方向転換することもあります。
権利化を前に重大な誤りがあることに気づくこともあるし、出願人において競合する新たな発明をすることもあるでしょう。
出願を取り下げることで、その出願自体が「最初からなかったことになる」ため、取り下げ後に内容を精査しなおして別の発明として特許出願することが可能となるわけです。
≪特許出願の放棄とは?≫
取り下げとよく似た手続きが放棄です。
出願後に特許庁に対して意思表示するという点では取り下げと大きな差はありませんが、概念的にはまったく異なります。
取り下げは「その出願は最初からなかったことにする」という手続きです。
最初から出願自体がなかったことと等しくなるため、出願内容に重大な誤りがあるなど再出願を予定している場合などに適しています。
一方の放棄は「出願はしたが権利化を望まない」という性格を持っている手続きです。
この違いは、従来は大きな意味を持っていました。
放棄は「最初からなかったことに」という性格を持ち合わせていなかったため、放棄によって権利化は叶わないとしても先願権は残されていたのです。
つまり、自身の発明が権利化できないとしても、後発で同様の発明をした別人の権利化を阻むことができていました。
旧来の知的財産保護の手法として、放棄は「ノウハウを守るためにブラックボックス化する方法」として多用されてきました。
この点は、平成10年の法改正によって放棄によっても先願権は残されないように変更されています。
つまり、現在においては取り下げと放棄に差はないと考えられます。
≪取り下げ・放棄の方法≫
特許出願の取り下げ・放棄ができるのは出願人のみですが、その手続きに関してのみに限った特別授権がおこなわれている代理人、または包括的に一切の手続きの代理権を与えられている特別管理人でも手続きは可能です。
また、共同出願にかかる特許出願であれば、権利の共有者にとって重大な影響があるため、共同出願人の全員が手続きをおこなう必要があります。
取り下げ・放棄には、出願取下書または出願放棄書の提出が必要です。
出願取下書または出願放棄書が受理されると、たとえ審査の途中であっても、特許庁に属している対象の出願手続き自体が消滅扱いとなり、審査も終了されます。
≪取り下げ・放棄で公開を防ぐ場合の注意点≫
特許出願の取り下げ・放棄によって公開を防ぐには、手続きにタイムリミットがあることを意識しておく必要があるでしょう。
出願された特許は1年6か月後に公開されますが、それまでに手続きすれば公開を防げるわけではありません。
特許公報の発行が進められている段階で手続きをしてもそのまま掲載されることになるため、公開を防ぐためには出願から1年4か月以内に手続きをおこなう必要があると心得ておきたいところです。
また、1年4か月を過ぎて取り下げ・放棄をおこなう際は、特許庁の方式審査課に連絡して公開中止を望む旨を伝えることをおすすめします。
取り下げ・放棄は高度な判断を要します。
また、時間の制約があるため取下書や放棄書の作成に間違いがあってはなりません。
特許出願の取り下げ・放棄を検討する際には特許事務所にアドバイスを請いサポートを受けるのが得策だといえるでしょう。
≪ネットの情報だけでチャレンジするのは危険!≫
特許に関する手続きは、知的財産に関するある程度の知識があり、経験を積んでいれば、自力でも可能です。
また、これまでに経験がなくても、インターネットで検索すれば「自分でやる◯◯」のようなページがたくさんヒットするので、ネットの情報さえあれば自力で手続きを進めることも可能でしょう。
ただし、ネットの情報が常に最新のものであるという確証はありません。特許の取り下げ・放棄については、平成10年の法改正以前の情報が含まれていることがあります。
古い情報を信じてしまい、放棄によって他者の権利化を防ぐ手法として放棄しても、現在においては意味がありません。他者に対する対抗策として放棄し、万全だと安心していてもまったく安全ではないのです。
最終的な手続きは自力を選ぶとしても、取り下げ・放棄にどのような効果があるのか、実際に手続きをした場合にどのような状態になるのかは、専門家にアドバイスを受けるべきでしょう。
特許の取り下げ・放棄を検討している、または権利化までは望まないが他者の権利化を防ぎたいと考えている場合は、信頼できる弁理士が所属する特許事務所に相談するのが得策です。弁理士に一任すれば、取り下げ・放棄にかかる手続きの手間が解消できるだけでなく、他者の権利化を防ぐ別の方策についてもアドバイスが受けられるでしょう。
費用を抑えるためにネットの情報に頼って自力で手続きをするのもひとつの方策ではありますが、まずは弁理士に相談することを強くおすすめします。