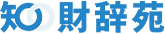目次
特許権には「産業上の利用可能性」という要件があります。
産業の発展が期待できる発明こそ特許権が与えられるということです。
特許権は一定期間の発明の独占を約束しますが、その先には広く発明を利用して産業の発展に寄与することが期待されているわけです。
つまり、特許権によって独占が認められてはいますが、発明は広く利用されるべきだという背景がベースにあるわけです。
そこで登場するのがライセンス契約です。
ライセンス契約は、他社が発明した特許に対して、対価を支払って「利用させてもらう」という契約のことです。
≪ライセンス契約とは?≫
ライセンス契約は「使用許諾契約」とも呼ばれます。
つまり、特許権者が契約者に対して発明の使用を許可するものです。
もちろん「無償で」というわけにはいきません。
特許権を得た発明は、出願の日から20年にわたって権利が保護されますが、その後は広く一般が利用可能となります。
出願から20年を待てば誰でも発明を利用できるようになりますが、その日を待たずに利用したければ対価を支払って許諾を受ける必要があります。
また、金銭を支払って許諾を受けるほか、自社が保有する特許権の使用許諾を対価とすることも可能です。
このようなライセンス契約の形態を『クロスライセンス契約』と呼びます。
≪ライセンス契約を結ぶ前の注意点≫
「あの発明を自社でも利用したい」と考えて、大した調査もせず、検討も重ねずに早々に特許権者とおぼしき相手とランセンス契約を結ぶのは得策ではありません。
ライセンス契約を結ぶ前には綿密な調査を徹底する必要があります。
まずは相手が真に特許権者であるのかを調べるべきです。
特許権者ではない相手とライセンス契約を結んでも何ら効力は生じません。
真の特許権者から侵害を訴えられることにもつながるので、特許庁から取り寄せた資料でしっかりと確認する必要があります。
ライセンス契約の範囲も十分に検討すべきでしょう。
契約の効力が及ぶ範囲を誤ると、せっかくライセンス契約を結んでも自社にとって利用価値がないものになることがあります。
ライセンス契約の期間にも注意したいところです。
契約期間が短いとライセンス料は割高となり、また無用に長いと長期的に有用であるかが不透明でありムダが生じるおそれがあります。
許諾される地域にも気を付けましょう。
特に国外への進出を果たしている、今後は国外へと市場をのばす展望がある企業であれば、国内のみのライセンスであれば国外での利用は許諾されません。
ライセンス料の額や支払い方法も十分に検討するべきです。
どんなに「使用したい」と考えても、費用対効果が低いまたはマイナスになるようでは企業として有益なものだとはいえません。
これら様々な条件をしっかりと検討し、ライセンス契約の締結を慎重にすすめるべきでしょう。
≪ライセンス契約の締結は特許事務所に相談を≫
ライセンス契約の締結には、契約の有効性や企業にとっての有益性を多角的に判断する必要があります。
ライセンス契約が真に有効なものなのか、自社にとって有利な内容となっているのか、著しく不利な条件での契約になっていないかなどのチェックは、知的財産権の専門家である弁理士のアドバイスを受けて判断すべきでしょう。
また、弁理士のチェックを受ければ、本当に自社にとって利益があるのかを総合的に判断してもらうこともできます。
自社だけの判断ではこれだけの多角的なチェックをおこなうのは困難です。
他社が持つ特許権をライセンス契約によって利用する場合は、まずは信頼できる弁理士が所属する特許事務所に相談し、アドバイスを受けましょう。
あわせて読みたい