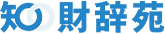目次
商品やサービスをリリースしながら市場で一社独占を貫くことは想像以上に大変なことです。
どんなに機能性に優れ、先進的かつリーズナブルで、独創的なものであったとしても、自社の商品やサービスのスペックを語るだけのアピールではライバル社をリードし続けることは難しいでしょう。
そこで利用されるのが、自社と他社の商品・サービスを比較して、いかに自社が優れているのかをアピールする「比較広告」という宣伝手法です。
比較広告という手法は以前から存在するものですが、知的財産権を念頭に考えるとある問題が発生します。
比較広告を用いる際は、他社の登録商標を自社の広告に掲載することとなります。
すると、その広告は他社の登録商標を無断で使用していることになるため、他社の商標権侵害を犯すことになるのではないでしょうか?
ここでは、比較広告と商標権侵害の関係を解説していきましょう。
≪比較広告は商標権侵害にあたらない?≫
比較広告では、自社と他社の商品やサービスを並列して表示することでどちらが優れているのかをアピールするのが基本です。
たとえば、A社がシェアを争っているB社との比較広告を作成する場合は、A社の商品がいかにB社の商品よりも優れているのかをさまざまな角度からアピールします。
すると、A社主導の広告の中にB社の登録商標が登場することになります。
もちろん、比較広告だとわかっていれば事前にB社が使用を許諾するはずもなく、A社は自社の広告内で無断でB社の登録商標を掲示することになるわけです。
こうなると、ただでさえ比較広告を打たれてしまって立腹しているB社としては「当社の登録商標を無断で使用している」と商標権侵害を主張したくなるのも当然でしょう。
ところが、結論をいうと比較広告のために他社の登録商標を無断で使用したからといって、商標権侵害にはあたりません。
≪「サントリー・黒烏龍茶」訴訟の実例≫
比較広告の事例として代表的なのが平成20年に判決が下された「サントリー・黒烏龍茶」訴訟でしょう。
ある企業が、サントリー社が販売している登録商標「黒烏龍茶」を比較対象に取り上げて「ポリフェノール含有量2070mg 約70倍 サントリーなんかまだうすい!」と表示したことでサントリー社が商標権侵害を訴えた事例です。
この事例も、やはりサントリー社の訴えはしりぞけられ、商標権侵害は認められませんでした。
裁判所の見解としては次のとおりです。
“ 比較広告を掲示した主は、商品の比較のために登録商標を用いたに過ぎず、自他商品の識別機能として用いられたわけではないため、商標として使用されたことにはならず、商標権侵害は成立しない。 ”
単純に比較の題材として使用されたに過ぎない場合は、登録商標といえども「商標としての機能を有していない」と判断され、比較広告では商標権侵害は成立しないという現代のモデルケースとなりました。
≪商標権侵害にあたらなくても他の法令違反になるおそれはある≫
商標権侵害にならないのであれば比較広告には何ら問題がないのかというと、それは間違いです。
比較広告には商標権以外の問題があります。
サントリー社は、商標権侵害だけでなく「商品を中傷した」として不正競争防止法違反も訴えました。
日本弁理士会近畿支部のホームページでは「客観的に実証できる要素について、正確な比較結果を公正な方法で掲示する場合、比較広告は違法にあたらない」と解説しています。
この解説のとおり、客観的な数値などを用いて比較したに過ぎない本件は何ら違法にあたらないというのが相手側の主張ではありましたが、この訴訟では相手側の「ポリフェノール2070mg」という表示が正確ではありませんでした。
たしかに、商品を手にする消費者が重要視する成分の表記に誤りがあったとすれば「客観的に実証できる要素について正確な比較結果を公正な方法で掲示している」とはいえません。
よって、サントリー社の訴えのとおり不正競争防止法違反が成立し、広告の差し止めと損害賠償請求が認められる結果になったのでした。
≪比較広告の掲載時は弁理士に相談を≫
自社の商品・サービスをより魅力的に演出するには、自社と同等または自社よりもシェアが大きな商品・サービスと比較して優れていることをアピールする手法が非常に有効です。
比較広告はこの側面で強力な訴求力を持っており、しかもインパクトも強力であるため、適法に掲示することができればシェア拡大に大きく貢献することは確実です。
ただし、商標権の問題だけでなく、不正競争防止法や景品表示法などにも配慮する必要があるため、安易に比較広告に手を出すのではなく、制作の段階から専門知識に基づいたアドバイスを受けるべきでしょう。
比較広告の掲示が計画された場合は、プランの初期段階で特許事務所に相談し、弁理士からのアドバイスを受けて紛争を回避できる内容にすることが賢明だといえます。