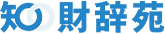目次
特許を複数の個人・団体の共同名義で出願する共同出願の場合は、権利一体の原則を意識した特許請求の範囲を意識した権利範囲の設定が重要です。
権利範囲の設定を誤ってしまうと、共同出願者によって特許の一部を利用されてシェアを奪われるおそれがあります。
特許の共同出願で失敗するケース

例えばA社とB社が共同で発明した商品について、A社・B社の共同で特許を出願したとします。
この発明の特許請求の範囲は「①と②と③で構成された④」であったと仮定しましょう。
特許の権利範囲は「権利一体の原則」に従って決められます。
権利一体の原則とは、特許発明を構成する要素全体を含んで権利範囲となる、という原則です。この場合の発明を構成する要素とは、願書に添付した特許請求の範囲に基いて定められるものであり、特許請求の範囲に記載された用語の意義は、同じ願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して解釈されるものです。
特許を共同出願した場合、原則的には、特段の契約がなければA社とB社は平等な立場であり、お互いが自由に実施権を持つことになります。
このような前提があった上で、A社が独自に「①と②のみで構成された⑤」を開発したとします。
B社は、「①と②の部分」を別に使用されていることに反発しました。
ところが、A社は①と②を使用しても③を使用していないので、A社は共同権利者であるB社に何ら承諾を得ることなく「①と②のみで構成された⑤」の実施が可能となりました。
A社は単独でシェアを拡大して急成長し、B社はA社と共同で特許を取得した商品の売れ行きが伸びず業界での地位が衰退していったのです。
共同出願において重要となる「権利範囲」

前項で挙げたケースの問題点は、A社が、B社とともに出願した特許の権利範囲の一部を利用して新たな製品を生み出したところにあります。
A社とB社が共同出願した発明は「①と②と③で構成された④」です。
③を除外して①と②のみで構成された⑤は、④の一部であっても特許請求の範囲に記載されていないので権利範囲外となります。
このケースでは、権利範囲を「①と②で構成された⑤」と「①と②と③で構成された④」に分けて定義し、それぞれどの範囲を共同出願とするのか、単独出願とするのかを十分検討しておけば回避できたはずです。
共同出願は、コストやリスクを分散できるというメリットを享受できる反面、技術面で他者に情報を提供することにもなるというデメリットもはらんでいます。
自社が守るべき技術は適切な権利範囲を設定して保護していく必要があるのです。