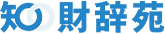目次
≪トラブルも多い?共同研究契約≫
知的財産保護の意識が非常に高まっている現代において、知的財産を武器として市場に乗り出すことは非常に重要です。
ところが、自社が持つ特許などの知的財産やノウハウだけでは市場で勝利を得ることができないと予測すれば、他社や研究機関などと協力して新たな商品やサービスの開発に乗り出すことがあります。
これが知的財産における『共同研究』と呼ばれる戦略です。
共同研究によって新たな知的財産が生み出され市場を独占した例は数多く、市場競争が激化している現代においては非常に協力な武器となります。
ただし、安易に共同研究に持ちこむことは望ましくありません。
共同研究はトラブルに発展することも多く、不用意な共同契約は自社にとって大きなマイナスを生むこともあるのです。
単に研究の失敗などであれば一時的な経済的損失が生じるだけで済むかもしれませんが、共同研究においては契約を軽視してしまうと自社の知的財産の価値を著しく損なうことにもなり得るのです。
そのため、共同研究においては必ず契約内容を吟味し、後のトラブル発生の回避に努めなければなりません。
また、最近の共同研究では、企業と大学などの研究機関が連携しておこなう機会が増えています。
大学などの研究機関では、企業と比べると知的財産に対する意識や経験が圧倒的に不足しています。
そのため、共同研究に対する認識がないまま研究者が無断で特許を出願したり、企業の特許出願に対して自身の権利を主張するなどといったトラブルも多発しています。
共同研究においては、契約に基づいておこなわれていることを明確にする必要があるでしょう。
≪共同研究における特許権利の持分は何に影響するのか?≫
共同研究契約においてトラブルに発展しやすいのが『特許権利の持分』についてです。
この『持分』について誤った認識を持っている企業や知財担当者は非常に多いので、トラブル回避のためにも、改めて特許権利の持分について認識を深めておいたほうが良いでしょう。
特許権利の持分に関して誤解が表面化するのはライセンス契約を締結する場合です。
たとえば、ある共同研究によって得られた特許が、A社60%・B社40%の持分で共有されていたとします。
A社がこの特許を第三者にライセンスする場合、特許を共有しているB社の承諾を必要とします。
当然、A社はB社に対して承諾を得ようとしますが、B社がこれを承諾しなかったとしましょう。
すると、A社が「持分は当社の方が上なのだから、承諾するべきだ」と主張し始めるのです。
この解釈には大きな誤りがあります。
特許の持分は、金銭的価値をはかるために用いられるものです。
出願や登録にかかる費用の分担、実施料・ライセンス料の配分、第三者による特許侵害の賠償金や売却した際の配分などに影響を与えます。
つまり持分は、ある特許権に対しての取扱いに優劣をつけるものではありません。
特許権の持分について、議決権のような力配分を持っているとの認識を抱く企業や知財担当者が多いため、この点は改めてチェックしておくべきでしょう。
≪共同研究契約を締結する際の持分の決め方≫
共同研究契約における持分は、契約者間で自由に取り決めることができます。
そのため、持分に関しては共同研究を開始する前に契約者間で綿密な協議を重ねたうえで決定されるべきであって、その内容は共同研究契約を締結する書面に明記しておくことが必須となります。
持分は、双方に均等として50:50にするのが一般的です。
これは、民法第250条において「共有財産の各共有者の持分は相等しいと推定される」と規定されているためです。
よって、仮に共同研究契約を締結する段階で持分の協議がなされなかったとしても、民法の定めによっては50:50に等分されることになります。
ただし、研究の対する労力や資金投入の差、共同研究に際して提供される知的財産やノウハウの有無、研究への貢献度に応じて差をつける場合もあります。
つまり、不均等な持分を設定する場合には、民法の基本原則に反するため、契約書において双方が合意したことを担保する必要があるということになります。
共同研究契約を締結する際には、特許権利の持分を協議して契約書面に明記する必要がありますが、研究過程や権利化後に実施していく中で共同研究者から不満を訴えられるケースも考えられます。
共同研究の内容や過程、その結果によって生み出される特許の性質などによって総合的に判断する必要があります。
その判断は、知的財産の知識と企業活動の関係に精通した弁理士にアドバイスを請うことで合理的な結論を見ることができるでしょう。
共同研究を進めるにあたっては、共同研究についての知識と経験が豊富な弁理士が所属している特許事務所に相談しておくとよいでしょう。