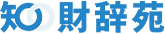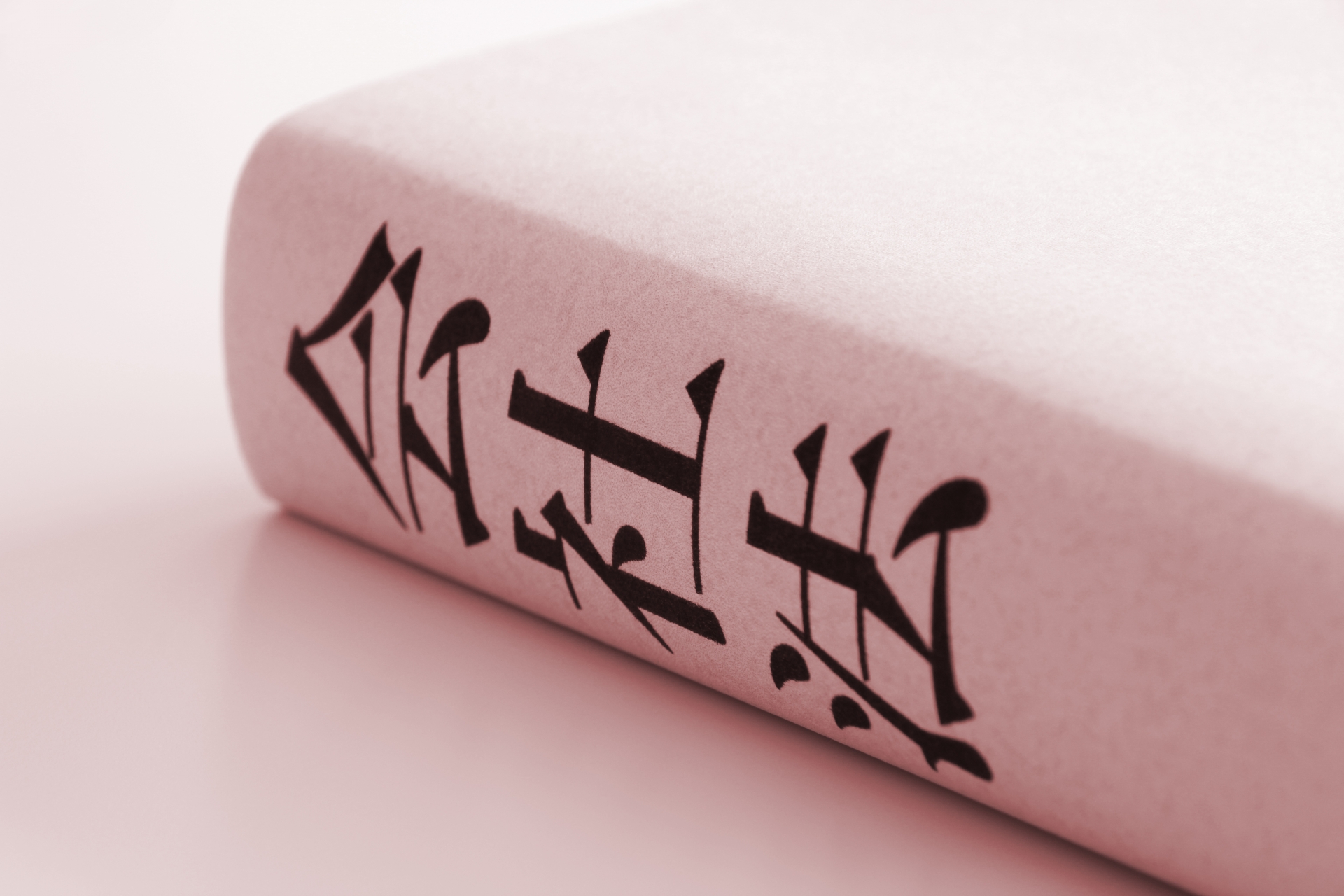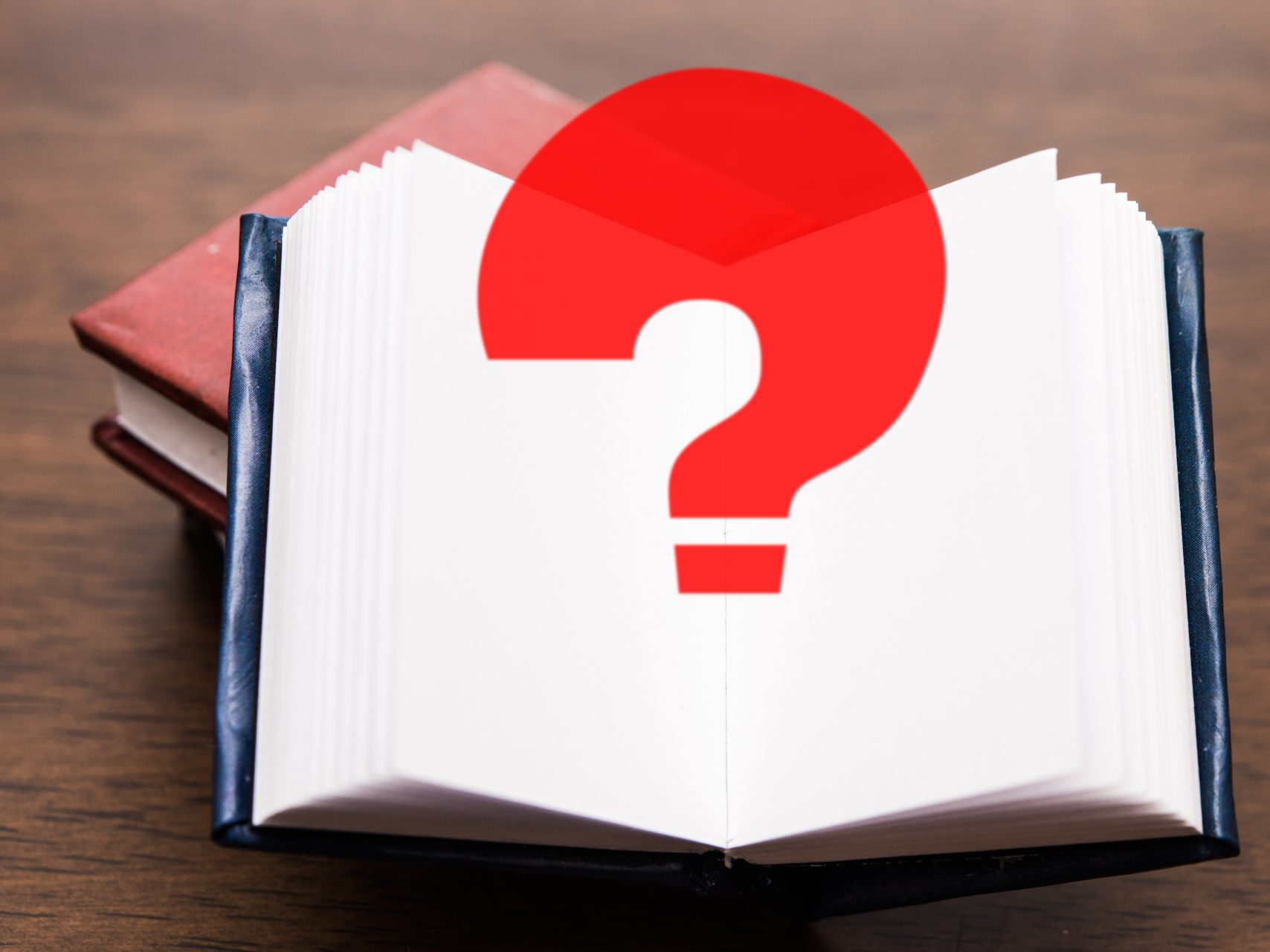目次
≪商標権侵害が発生した場合の損失≫
自社の商標を第三者が無断で使用していることが発覚すれば、素早い対処が必要となります。
もしこれを看過していれば、甚大な損失を被ることは間違いありません。
第三者に商標を侵害された場合、どのような損失を被るのでしょうか?
まずはシェアの侵害です。
商標は商品やサービスの識別に活用されているのであるから、商標を侵害されれば、消費者は自社の商品・サービスだと誤認してしまうおそれがあります。
同じ商品・サービスを販売されてしまえば、シェアを侵食されてしまうことは避けられないでしょう。
ブランド力の低下や信用の失墜も深刻です。
自社の商標を利用された粗悪な商品・サービスが市場に出回ってしまうと、自社の商品・サービスが粗悪なものだと誤認されてしまい、ブランド力が著しく低下してしまうおそれがあります。
「◯◯社の製品には粗悪品が多い」などという風評が広がり信用を失ってしまえば、信用を取り戻すためには多大な時間と労力を費やすことにもなるでしょう。
商標侵害による被害が深刻化してしまう前に、早急に対策を講じておく必要があります。
≪商標権侵害を発見!まずは警告書を発する≫
商標権侵害を発見したら、まずは相手にこちらの意思を伝えることを優先すべきでしょう。
警告書を発して、早急に商標の使用を中止し、場合によっては損害賠償請求などの法的手段をとることも辞さない姿勢を示すことが大切です。
警告書を発していれば、相手は以後は「知らなかった」で済ますことができなくなります。
言い方を変えれば、警告書を送付することで「この時点からは商標権侵害が発生していたことを認識していた」という起点を設けることができます。
警告書には、自社の姿勢を示すこと以上に「相手の行動を封殺する効果がある」という面で効果的であることに注目すべきでしょう。
≪要求の着地点を決めて、要求に応じなければ訴訟へ≫
警告書を発する限りは、自社としての要求に着地点を決めておく必要があります。
単に侵害行為をやめればそれで良いのか、市場に出回っている商品を回収する必要があるのか、侵害によって得られた利益を賠償金として支払うことを求めるのかなど、自社が求める要求の最終着地点を明確にしておきましょう。
いきなり訴訟をすることも不可能ではありません。
しかし、訴訟には多大な労力がかかります。
しかも、抗戦する姿勢を示されてしまうことも多いので、まずは示談による解決を目指し、あまりにも自社の要求と相手の回答がかけ離れているのであれば次のステップへと移行すると計画しておいたほうが良いでしょう。
訴訟に踏み切る場合は、まずは差止請求を考えるべきです。
差止請求を申し立ててこれが認められれば、侵害された商標を使用している商品の販売、サービスの提供を法的な拘束力によって中止させることが可能になります。
その上で、侵害によって被った損害について賠償を求めることになります。
≪あえて問題にしないという方針もあり得る?≫
商標侵害を「あえて問題にしない」という方針もある、といえば多くの方は驚くかもしれません。
ところが、あえて商標侵害を指摘せず問題にしないことで、世間への認知度を高めて結果的にはシェアが拡大するということもあり得ます。
この手法には2つの条件があります。
まず一つ目の条件は「相手が侵害を認識していなかったこと」です。
悪意なく侵害行為をおこなっていることが大前提であって、攻撃的な意図を持っていたり、侵害を知りながらシェアを侵食しているような状態であったりすれば、黙認することは得策ではありません。
二つ目の条件は「相手が大企業であること」で、この条件が最も重要です。
相手が大企業であれば、自社の資本力ではできなかった展開を見せることがあります。
大企業のおかげで市場が拡大すれば、結果的には売上げが伸びることが期待できるのです。
侵害を知っていて指摘しないことは違法ではないので、侵害を指摘するのは大企業による侵害の恩恵を授かってからでも良いでしょう。
ただし、この「あえて問題にしない」という手法は非常に高度な問題でもあります。
判断を誤れば、自社のシェアとブランド力に甚大なダメージを負うおそれがあるのです。
商標侵害が発覚し、どのような対応を取るべきなのかを検討する際には、商標に関する知識が豊富で、商標侵害に対する対抗策を熟知している弁理士の判断を仰ぐためにも、早期に特許事務所に相談しましょう。