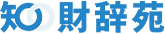目次
意匠登録では、出願した意匠が特許庁の審査を経て登録に至った場合、意匠公報によってその意匠の内容(デザイン)が公開されます。
公開されたデザインは意匠権によって守られるため、第三者による模倣に対しては強く権利を主張することができますが、企業の経営戦略面からすれば「どのようなデザインを意匠登録したのか?」を競合他社や消費者に知られたくない時期もあるでしょう。
この「公開」と「秘密」の希望のジレンマを解消するのが「秘密意匠制度」です。
秘密意匠制度の概要
秘密意匠制度とは、意匠法第14条の規定に則り、登録となった意匠について登録日から3年間を期限として秘密にすることができる制度です。
秘密意匠は、出願する時と登録料を納付する時の2回のタイミングで申請できます。
これ以外のタイミングでは、申請できないため注意が必要です。
申請には、秘密意匠の設定登録料として5,100円かかります。
秘密意匠制度が有効な分野とは?
秘密意匠制度が有効に働く分野といえば、やはりデザインが購買意欲を決める分野でしょう。
たとえば自動車業界は、各自動車メーカーが独自に開発したデザインの車が次々とリリースされています。
ユーザーは「次はどんなデザインの車が発売されるのか?」と期待しながらメーカーの発表を待ち、正式発表の日まで秘密を貫いてきた新車のデザインの斬新さに購買意欲をかき立てられるのです。
これが、企業が意図した発表よりも前に新デザインが意匠公報で公になってしまった場合、商品の発表時の消費者の購買意欲が減退してしまう可能性があります。
そのため、企業が計画している製品発表の前に登録した意匠を公開されたくない場合は、登録料を納める際に秘密意匠の設定を忘れないように申請しましょう。
自動車業界のほか、証券用紙・パチンコ機器・包装用の容器や瓶・携帯電話やスマートフォン・エアコンや冷蔵庫などの家電製品・ゲーム機・芳香剤や脱臭剤・便器などの分野において、有効に活用されている事例が多くなっています。
いずれの分野も、いわゆる「流行り廃り」の傾向が強い分野であり、メーカー側が新製品のデザインの発表を戦略的におこなうことで、購買意欲を上下させる分野だと言えるでしょう。
秘密意匠制度の要件
秘密意匠制度を利用するためには、制度利用の請求をおこなう必要があります。
請求をおこなうタイミングは、
- 意匠登録の出願時
- 登録時
のいずれかです。
秘密にする期間は3年を上限に設定することができ、期間中に延長・短縮を請求することも可能です。
秘密意匠制度のデメリット
秘密意匠制度には、登録した意匠を第三者に知られないことで、消費者の購買意欲の損失を防ぐというメリットがありますが、デメリットもあります。
それは「過失推定」が適用されないことです。
登録した意匠を真似してきた相手に損害賠償を請求する場合、相手に「過失があること」が必須の条件になります。
秘密意匠を設定しない通常の意匠権であれば、第三者に意匠を模倣された場合は、「侵害行為に過失があったとみなされ」ます。
意匠公報として公開しているのだから、製造・販売等の前に調査しなかった側に過失があると判断されるということです。
すなわち、権利者側が模倣者側の過失を証明する必要がありません。
ところが、秘密意匠の場合、公報自体は公開されるものの内容は公開されないため、第三者がしっかり調査をしたとしても意匠の詳細を知ることはできません。
よって、秘密意匠が設定されている期間は模倣者への過失推定は適応されず、権利者側が相手の過失を証明しなければなりません。
秘密意匠を設定し、偶然他の人が類似する製品を販売した場合、相手側の過失を証明できないときは相手に損害賠償を請求することはできません。
相手の過失を立証できず損害賠償を請求するのが難しい場合でも、商品の差し止めを請求することは可能です。
ただし、通常の意匠権とは異なる手続きが必要になります。
まず、いきなり差し止め請求することはできません。
先に登録した意匠権の内容を証明する書面(※特許庁長官の照明を受けた書類)を提示して警告をする必要があります。
その後、相手がやめないのであれば差し止め請求をするという流れになります。
また、秘密意匠制度といえどもいかなる場合も秘密を貫けるわけではないという点も注意が必要です。
意匠権者の了承を得た場合のほか、その秘密意匠と同一または類似した意匠を出願した第三者が生じた場合には、審査・審判・再審・訴訟の当事者や参加者の請求によって開示されることがあります。
このように、秘密意匠制度は企業戦略の面でのメリットはありますが、デメリットも大きいため、必要な場合、必要な期間にのみ設定するのが良いでしょう。
登録した意匠について秘密意匠制度を利用するべきかどうかの判断が難しい場合は、弁理士に相談してアドバイスを求めるのがお勧めです。