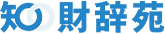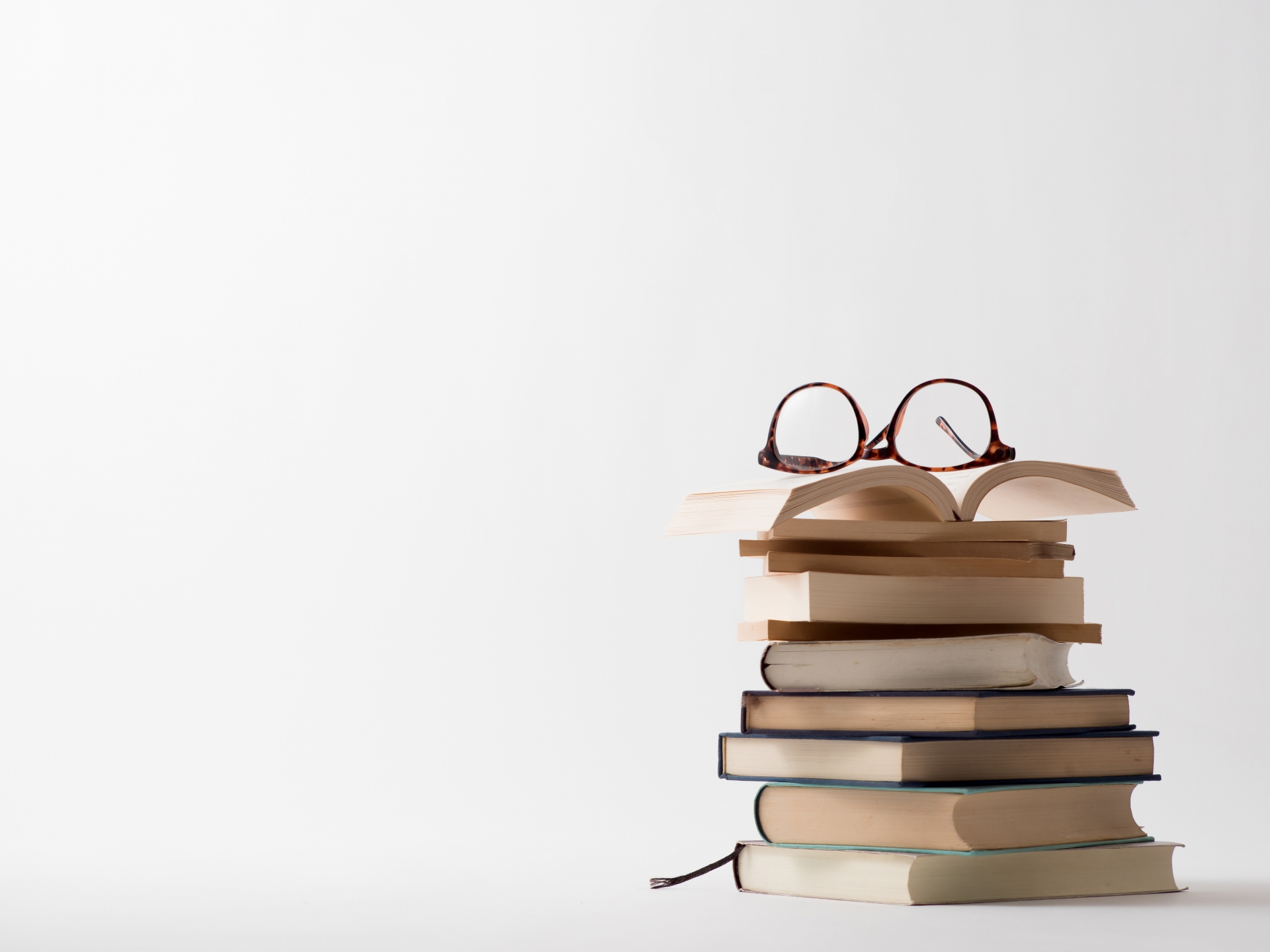目次
特許は簡単にいえば「自身のアイデアを他者に真似させないための盾」だといえます。
特許権を得るためには特許庁に出願し、各審査をパスして特許査定を受ける必要があり、登録に至れば、特許は自身に大きな利益をもたらしてくれることになります。
もし新たな発明をすればもれなく特許権を取得して利益につなげたいと考えるのは自然ですが、特許出願には失敗事例も多くあります。
ここでは、特許出願に関する失敗事例を紹介しましょう。
出願前の調査にまつわる失敗例

特許を出願するにあたっては、先行する特許が存在しないかの調査が必須です。
特許権の要件としては『新規性』が挙げられるため、自分では新たな発明だと喜んでいても既に存在する発明であれば特許査定に至ることはありません。
そのため、J-Plat Patや商用データベースを利用して綿密に検索して、出願前調査を尽くすことになります。
出願前調査において最も失敗が多いのが、特許事務所に依頼せず自分で調査をした場合の検索ミスです。
使用するデータベースには差はありませんが、膨大なデータを効率よく検索するには、経験豊かな特許事務所のノウハウが活躍します。
出願費用を浮かせるために自分で完結させようとすると、調査が有効に行われず、結局特許を取得できない、という結果につながることがあります。
また、J-PlatPatでは出願されてまもない特許の情報が反映していないことがあり、検索のタイミングも重要となります。
開発初期や途中の段階で検索にヒットしなかったからといって安心していると、出願時にはすでに他者によって同じ発明が出願されていたというケースもあるので注意が必要です。
特許事務所に相談しながら進めていけば、適切な方法とタイミングで調査を実施してくれるので、リスクが低減されるでしょう。
公開にまつわる失敗例

新たな技術を発明すると、何らかの機会に発表してしまいたくなるものです。
例えば学会の研究発表、取引先へのプレゼンなどで発明を公開してしまうなどのケースが考えられますが、ここでも特許の要件に『新規性』があることを忘れてはいけません。
もし、これまでにない発明だったとしても、出願前に公開された事実があれば「新規性がない」として拒絶されてしまうおそれがあります。
この点は、特許の要件などを紹介するサイトや書籍でも紹介されることが多いためご存知の方が多いかも知れませんが、現実的には、出願を受けた特許がいずこかで公開されていないかという調査は、特許庁ではほとんどおこなわれていません。
そのため、出願前に取引先などに公開していても案外と登録に至るケースがありますが、ここで安心してはいけません。
問題は、特許成立後に競合他社などから指摘され、特許が無効とされてしまうおそれがあるということだと覚えておきましょう。
周辺技術や改良発明にまつわる失敗例

特許出願の際には、必ず周辺技術や改良発明をフォローして出願する必要があります。
ある発明を単体でのみ出願し、周辺技術や改良発明へのフォローを怠ってしまうと、競合する他社が先回りして周辺技術や改良発明の特許を取得してしまうことが考えられます。
特許を取得したもともとの発明のみで永続的にビジネスが成立するのであればそれで良いかも知れません。
しかし、問題となるのは、将来的に改良品をリリースしたりモデルチェンジを実施する際に、先回りした他者の特許を侵害してしまうケースが存在することです。
周辺技術や改良発明が他者に押さえられていると、改良品のリリースやモデルチェンジに踏み切ることができなかったり、他者とクロスライセンス契約を締結する必要が生じたりします。
せっかく特許を取得しても、これでは将来的なビジネスの幅を失ってしまうでしょう。
特許出願で失敗しないためには?

特許出願で失敗しないためには、ここで紹介した失敗例のポイントをおさえた出願を心がける必要があります。
ただし、特許を含めた知的財産の分野は非常に専門的であり、さらに実務には机上の学習だけでなく豊富な経験が必要です。
自身だけで特許出願を完結させようとすると、ここで紹介したような失敗に陥りやすいため、特許出願で失敗しないためには知的財産のスペシャリストである弁理士に依頼するのが最も有効な解決策だといえるでしょう。
費用面を心配する方も多いのも事実ですが、真に将来の経営にも役立つ有能な特許を取得するためと考えれば、費用以上の価値があることは間違いありません。