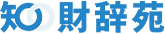目次
『著作隣接権』ってなに?
著作権について新たに勉強し始めた知財担当者にとって、『著作隣接権』という用語は耳馴染みのない言葉でしょう。
まず説明しておくと、著作隣接権とは「著作物を伝える人を保護する権利」です。
少し分かりにくいので詳しく説明していきましょう。
著作物の中には、伝達する人の協力がないと広く世の中に伝えることが難しいものが存在します。
その代表が『音楽』で、著作隣接権を与えられているのは「音楽を多くの人に伝える仕事の人に与えられた権利」だと考えれば良いでしょう。
著作隣接権を詳しく解説

著作隣接権が与えられているのは「実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者」だけです。
例えば、あるポップミュージックを『山田太郎』の名義でCDリリースするとしましょう。
(※山田太郎は、作詞作曲を行っていません)
まず、そのポップミュージックについて著作権を持つのは山田太郎ではなく作詞家・作曲家です。
とはいえCDリリースで名前を世の中に公表するのは山田太郎ですから、
山田太郎には『実演家』としての権利が保護されます。
実演家には、実名や芸名を名乗るための氏名表示権、同一性保持権、
生の実演や録音した実演について録音・録画・放送・送信を許諾する権利、実演が固定された録音物等を公衆へ譲渡する権利及び、放送やレンタルなどで報酬を受ける権利が与えられています。
さらに山田太郎名義のCDを販売するためには録音した音源をCDに焼き付けて大量生産することになります。
そのため『レコード製作者』の権利も保護されます。
レコード製作者には、レコードの複製・送信可能化・譲渡・貸与を許諾する権利、レコードが放送されたりレンタルされたりした際に報酬を受ける権利が保護されています。
つまり1枚のCDのウラには、作詞家・作曲家に保護された著作権と、
楽曲を実演する歌手やCDの製作会社に保護された著作隣接権が存在しているということです。
レコード製作者によってCD化されたポップミュージックは、テレビ放送などによって伝達され世の中の人に広く知られることになります。
そこで、テレビ局などは『放送事業者・有線放送事業者』としての権利が保護されます。
放送事業者と有線放送事業者には、複製権、大型スクリーンなどで放送するための伝達権、放送した番組をさらに別の事業者が放送するための再放送権、及び、送信可能化権が保護されています。
これらの著作隣接権は、原則実演・録音・放送からそれぞれ50年の間保護されます。
これから音楽に関する著作物について触れる機会がある知財担当者は、著作隣接権について深く知る必要があるでしょう。